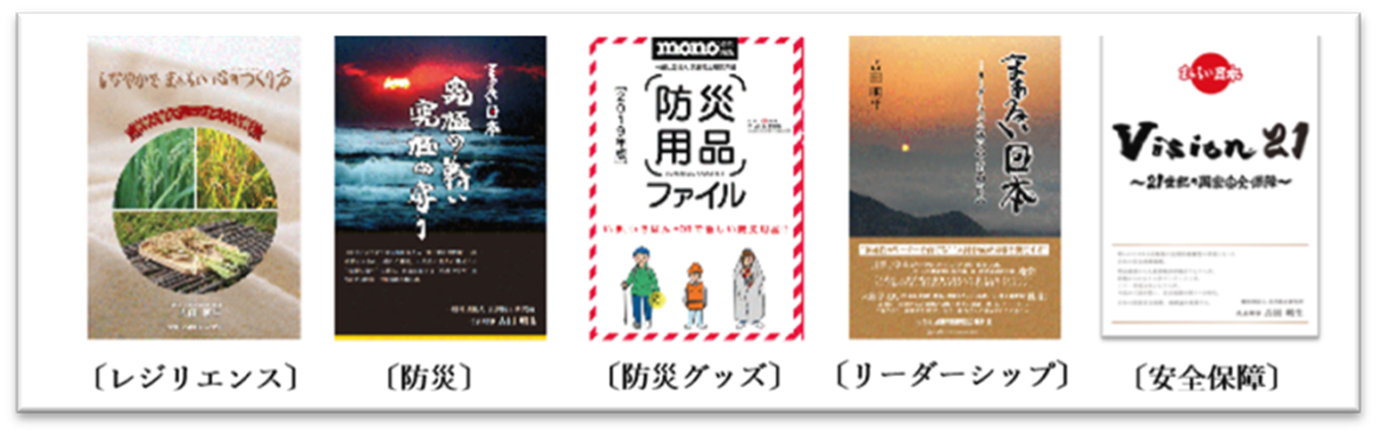最近、中共との外交関係がゴタゴタしていますが、もともと共産主義国は、資本家との闘争に勝つことを使命としている国ですから、資本主義国との戦いという「恐怖(強い不安)」を内外に印象付け、それを収めようとする平和や協調を唱えるプロパガンダによって「安心(安定への期待)」を与え、対象勢力からの譲歩を引き出して地歩を拡大し、最終的には「共産主義による平和(資本主義国の撲滅)」を達成しようという戦略を常用します。
それに用いる戦いの基本が「恐怖・安心の心理戦」です。
最近は「認知戦」という言葉が流行っていますが、本質は古代からある「恐怖・安心の心理戦」で、目的が「認知(意識)」に影響を与えることになります。
伝統的な「恐怖・安心の心理戦」について、簡単に解説します。

1 恐怖・安心の心理戦とは
恐怖(強い不安)と安心(安定への期待)を交互・対照的に提示し、人間の判断・行動・帰属意識を操作する戦いは、軍事、宗教、政治、マーケティング、組織統率、プロパガンダ、カルト、外交交渉など、あらゆる分野で利用されている普遍的な心理操作です。
2 基本原理
① 恐怖は、人を従属・集中・服従状態へ導く。
恐怖は、対処する方法を考えるよりも「逃げる・従う」方向に向かわせます。
拠り所へ依存しようとする気持ちを増大させるように「敵・味方の二元思考」へ誘導したり、迅速な意思決定を強いて「判断を単純化」させたり、「安全を確保してくれる者」への忠誠を感じさせたりするなど、恐怖によって主体的な思考を奪います。
②「安心(保護・恩恵)」は、信頼・忠誠を形成する心理的反応を生む方向に働く。
安心は、感謝・救済体験によるポジティブな意識を作り、保護してくれる存在への忠誠心や所属意識・帰属意を強くさせて、「ここにいれば大丈夫」というような自己肯定感を求めるようになります。
安心は、心理的な主体性を回復させ、帰属先を固定する方向に働きます。
③恐怖と安心を「セット運用」すると依存心が生まれる。
人は、「危機(恐怖・強い不安)から救済(安心)」への流れを体験すると、安心を与えてくれる存在だけが自分を危機から守ってくれる、と錯覚します。
これは心理学で、「救済体験による同調帰属(救済依存)」と呼ばれます。
心理戦では、この循環構造を作ることにより、相手の行動判断能力を奪います。
| フェーズ | 目的 | 心理効果 |
| ①恐怖の提示 | 緊張・危機感・無力感を覚えさせる | 判断停止・服従 |
| ②安心の提示 | 逃げ道・安全基地を用意する | 安堵と感謝 |
| ③安心への条件化 | 安心は服従・忠誠・協力の代価であると暗示 | 依存と忠誠 |
| ④恐怖の再提示 | 離反しようとする心への警告 | 離脱できない構造 |
3 用例の典型的パターン
●古代宗教
災厄・祟り(恐怖) → 祈祷が秩序維持の唯一の解である印象を与える
●軍事・戦争プロパガンダ
外敵脅威・民族浄化・滅亡の危機 →我々は守る側だと正義・正当性を主張
●カルト宗教・セクト型指導者
世界崩壊・地獄・不幸の強調 → 救われるのはここだけで、離れたら不幸になる
●組織統率・ブラック企業
失敗すれば責任、周囲が敵になる → ここで努力すれば安全・評価が得られる
●国家の統治技法
有事法・危機管理・戒厳・治安 → 強力な統治がなければ国家は崩壊する
●現代社会
「情報」を主役とし、「恐怖」で注意と依存を引きつけ、「安心」で優位を固定する。
| 恐怖のツール | 安心のツール |
| フェイクニュース | フィルターバブル(自分と同じ価値観の群れ) |
| 不安の可視化(災害・治安・経済) | 解決策を掲げる指導者・政党 |
| SNSによる炎上 | 承認・フォロー・コミュニティ帰属 |
| リスク報道 | 安心商品のマーケティング |
4 本質
人は恐怖によって従属し、安心に対して忠誠を示します。
恐怖・安心の心理戦の本質は、次の三つで表されます。
① 恐怖を煽りながら安心を与える者は、強い支配力を持つ。
② 恐怖と安心の組み合わせを見抜けない者は、簡単に心理操作される。
③ 安心は無条件であるべきで、代価を要求する安心は支配の手段である。
5 結論
思考停止を回避することが相手に支配されないための最大の防御となります。
恐怖の源が現実か誘導かを見極め、安心の供給者が無条件の安心を示しているのか、服従の対価を求めているかを判断しなくてはなりません。
複数の対応手段を持って一つの対応手段に頼らず、帰属先と自分の利益が一致していることを確かめ、考える時間を奪う情報を疑うことが大切です。